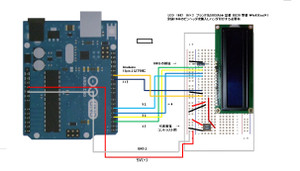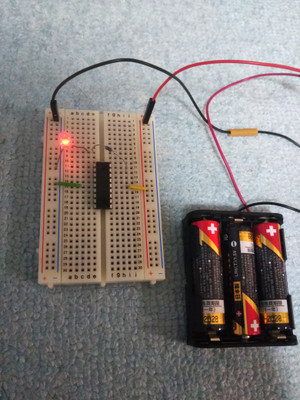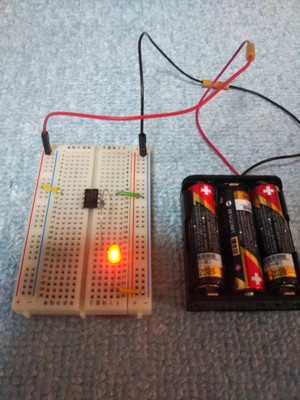(注意)PCを入れ替えによりMPLABを最新版(V5.45)XC8(V2.31)で再セットアップしたところ、下記説明のプログラムでコンパイルエラーを起こすようになりました。(2021年01月22日)
PCを入れ替え新たにセットアップしたXC8(V2.31)をアンインストールのうえ、Microchip社のアーカイブのダウンロードサイト(検索サイトで "XC8 Ver1 archive"で検索し「MPLAB Ecosystem Downloads Archive Microchip Technology」を探す)からXC8(V1.45)をダウンロードし、セットアップするとコンパイルでエラーがなくなりました。(この対策方法は、ネット検索で見つけました。)(2021年01月23日)
MPLAB(V5.45)付属のIPEでは、PICへの書き込みが出来ませんでしたので、アンインストールのうえ、MPLAB X (V5.15)にしました。(2021年01月25日現在)
■ 2020年03月20日 作成
2020年03月22日 修正
2020年03月25日 修正(#pragma config MCLRE = ON → OFFへの変更)
2020年06月23日 画像の追加
2021年01月21日 1.新規プロジェクト作成の誤字訂正(12F675→16F88)
MPLAB IDEv5.45の場合を追加
2021年01月25日 IDE / MPLAB訂正 コンパイラバージョン追記 MPLAB IDEv5.45の場合削除
2021年05月22日 MPLABXIPEの「Adbanced Mode→Password」の修正とボルトに関する補記の追加
2024年02月22日 ■手順 3.configの設定 誤記(Windows → Window)訂正
■参考にされる場合は、自己責任でお願いします。
■作成時の環境
OS / Windows10
IDE / MPLAB X V5.15
コンパイラ / XC-8 v1.45
PICkit 3
■準備品
ブレッドボード
LED
抵抗 330Ω(前後)
■手順
1.新規プロジェクト作成
IMPLABXIDEを起動 メニュー File → NewProject → Next →
Device → PIC 16F88を選択 → Next → PICkit3 →Next → ●xc8(v・・)[・・・] → Next →
ProjectName[例:16F88_led] → Finish
これで16F885_ledという新規プロジェクトが出来ます。
2.新規プロジェクトにプログラムを記述する場所を作成します。
・メニュー Windows → Projects → Projects[タブ] → 16F88_led「+」 クリック → Source Files上で右クリック → New→ C SorceFliles → File Name [newfiles] → Finish
3.configの設定
下記の部分を張り付ける。
・メニュー Window → Terget Memory Views → Configration Bits →
設定画面(何もせず) → 「Generate Source Code to Output」ボタンをクリック
すると設定が自動作成されるので内容(見えていない上の部分を含むすべて)をコピー
しプログラムの設定エリアに張り付ける。
当該ウィンドウ右上角のアイコンをクリックして閉じる。
但し、このままではLED点滅が不安定となるので#pragma config MCLRE = ON
を OFFに変更すること。
4.クロックの設定
クロックを以下のとおり記述
#define _XTAL_FREQ 4000000 //delay関数を使う為の設定 クロックは4MHz
5.動作のプログラム
void main(void){
OSCCON = 0x70; //0x70の指定で delay_ms(1000);のとき1秒待機
PORTA = 0x00; // PORTAを初期化
PORTB = 0x00; // PORTBを初期化
TRISA = 0x00; // PORTAの出力設定
TRISB = 0x00; // PORTBの出力設定
while(1) { // 無限ループ
RA0 = 1;
__delay_ms(1000); // 1秒の待ち時間
RA0 = 0;
__delay_ms(1000); // 1秒の待ち時間
}
return ;
}
////////////////////////////////////////////////////////////
全体のプログラムは以下のとおり
////////////////////////////////////////////////////////////////
// PIC16F88 Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
#include <xc.h>
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
// CONFIG1
#pragma config FOSC = EXTRCCLK // Oscillator Selection bits (EXTRC oscillator; CLKO function on RA6/OSC2/CLKO)
#pragma config WDTE = ON // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = OFF //ON→OFF 20200325 不安定のため変更 // RA5/MCLR/VPP Pin Function Select bit (RA5/MCLR/VPP pin function is MCLR)
#pragma config BOREN = ON // Brown-out Reset Enable bit (BOR enabled)
#pragma config LVP = ON // Low-Voltage Programming Enable bit (RB3/PGM pin has PGM function, Low-Voltage Programming enabled)
#pragma config CPD = OFF // Data EE Memory Code Protection bit (Code protection off)
#pragma config WRT = OFF // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off)
#pragma config CCPMX = RB0 // CCP1 Pin Selection bit (CCP1 function on RB0)
#pragma config CP = OFF // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
// CONFIG2
#pragma config FCMEN = ON // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor enabled)
#pragma config IESO = ON // Internal External Switchover bit (Internal External Switchover mode enabled)
//ここまでWindows→PIC Memory views→configlation Bitsで出力した内容の貼り付け分2020.3.20
#define _XTAL_FREQ 4000000 //delay関数を使う為の設定 クロックは4MHz
void main(void){
OSCCON = 0x70; // 0x70を指定するとDelay_ms(1000);で1秒待機
PORTA = 0x00; // PORTAを初期化
PORTB = 0x00; // PORTBを初期化
TRISA = 0x00; // PORTAの出力設定
TRISB = 0x00; // PORTBの出力設定
//TRISB = 0xFF; // PORTBの入力設定
while(1) { // 無限ループ
RA0 = 1;
__delay_ms(1000); // 1秒の待ち時間
RA0 = 0;
__delay_ms(1000); // 1秒の待ち時間
}
return ;
}
////////////////////////////////////////////////////
この内容で、コンパイルすると、
C:\Users\コンピュータ名\MPLABXProjects\16F88_led.X\dist\default\production
にHEXファイルが出来上がります。
6.PICkit3へのセット
PICkit3に16F88をセットします。
(18ピン用のセッティングが出来ていること)
7.MPLABXIPEによるプログラムの書き込み
MPLABXIPEを起動する。
Device → PIC16F88 → Apply → Tool → 接続されたPICkit3が表示されている → メニュ-→Settings →Adbanced Mode→ Password("microchip"画面下にも記載済) → Logon → 左側ウインドウのPower → Power Target circuit Tool の左側□にチェックする → 左側ウインドウのOperate → sourceのBrowseでHexファイルを選択 → Programをクリック → ok
これでPICに書き込まれるはずです。
なお、使用マシン環境の為か、"volts"に関するエラーメッセージが出ますので、IPEの左側ウインドウの Power → VDD: のボルト表示を5から4.8に変更すると書き込みすることが出来ましたので、このことも補記します。
8.配線
16F88のピン配置
右側真ん中のVDDピンはプラス(4~5V)
左側真ん中のVSSピンはGNDへ
右上から二番目のピンに抵抗を介してLEDの長いほうの線のプラスを接続し、
短いほうの線のマイナス側をGNDに接続します。
9.画像を添付
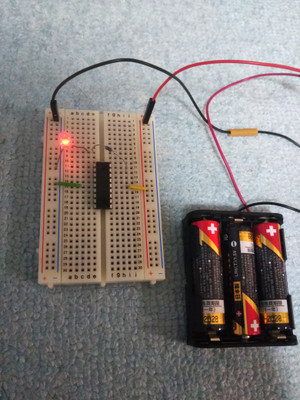
以上
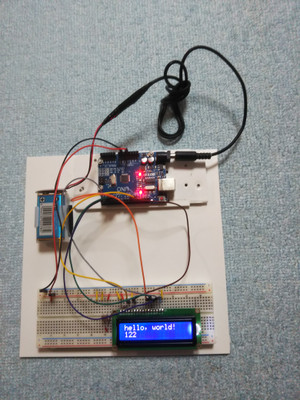 Aruduino互換機に9Vの乾電池を電源にLCD1602に表示させています
Aruduino互換機に9Vの乾電池を電源にLCD1602に表示させています